コラム③ 大野ゆたか ~創作ノート~4、5
コラム⑤ 大野ゆたか ~創作ノート~ 5
創作ノート1、2で、大野の貸本屋執筆時代(昭和32年(1957年)~35年)のエピソードを書いた。「呪われた宝石箱」「鉄人18号」「怪盗紳士ルパン 奇岩城」「怪盗紳士ルパン 水晶の栓」の4作品だ。
その後の調査で大野が執筆した貸本屋時代の書き下ろし作品は、更に2作品確認されている。「幽霊城の秘密」「暴力街」の2作品だ。PNが書かれていないため、作中に描かれたサインなどから、大野ゆたかの作品であることが確定された。
この2作品は「水晶の栓」直後に描かれたと思われる。大野の当時の記憶が薄れているため、その漫画コピーを見せて奥様の確認を仰いだ。執筆当時、大野の奥様がベタを塗った記憶があると話してくれた。幼馴染で一歳年上の奥様は大野と結婚、上京して同居した後は大野の唯一のアシスタントであった。枠線、ベタ、消しゴム、ほぼ全てを担当した事があると言う。
昭和34年「少年マガジン」が講談社から創刊される。当時の牧野編集長は漫画家おおともよしやす氏の原稿待ちの際に部屋に置かれていた大野の「怪盗紳士ルパン奇岩城」に目を止める。新人漫画家を探していた牧野氏は早々大野に連絡を取り、サンプル漫画の提出を依頼する。「怪盗紳士ルパン」は中村書店での売れ行きは好調であり、シリーズは続く予定であった。しかし、講談社からの仕事は週刊連載であり、当時の執筆ペースではとても書き下ろしは続けられないと判断し、大野はルパンシリーズの続投を丁重にお断りする。
この時、大野は35年に結婚し、同じ九州出身の漫画家高井研一郎氏達と住んでいたアパートをすでに引っ越していた。
少年マガジンに提出したサンプルは、牧野氏の興味を惹くには十分な内容だった。早速連載の依頼が来た。昭和35年7月3日「少年マガジン」27号から連載が開始されたゼロ戦闘機乗りの戦記物「日の丸一平」である。この作品が大野の週刊誌デビュー作となる。
「日の丸一平」の原作者は軍事専門誌「丸」編集長の高城肇(はじめ)氏だ。連載が始まった年は太平洋戦争が終結してから15年が経過していた。終戦直後の日本は出版、放送等GHQの管理下にあり、日本の軍事についての情報の一般開示は厳しい制約が引かれていた。終戦から3年程して航空戦力(ゼロ戦など)の図面、写真が公開され、更に海軍の戦力(軍事機密戦艦大和など)について「丸」に公開されたのは7年以上の歳月を有した。子供達に対しては戦争思想は厳禁で制限が引かれていたため、少年誌の戦争記事、コミック、プラモデルの販売などGHQの管理期間が終了するのを待たざるを得なかった。そんな中で軍事専門誌「丸」はいち早く太平洋戦争の情報を掲載することが出来た専門誌だった。高城氏は副業で神保町の喫茶店を経営していた。そこで大野は彼から原作を渡された。原作に盛り込まれたエピソードの一部は戦争の史実に基づいた物であり、当時他の紙面では全く知り得ない情報も多かった。それらに目を通した大野は、極めて専門性に富んだ戦記物を執筆することができた。他に描かれていた戦争物コミックはほとんど空想で作られリアリティに欠けた作品ばかりだった。「日の丸一平」の連載は4カ月ほど続いた。ラバウル航空隊に所属する主人公一平は日本に帰れるチャンスに恵まれるが、内地に帰れる切符を敢えて捨て、戦場で戦い続けて行く道を選ぶ。大野は作中で一平の死を描いた記憶はない。メカ物を描いた経験のなかった大野はそれまで以上に奥さんの助けを借り、一生懸命作品に取り組み続けた。

右ページ登場人物の一番下の列、一番左側の人物の持っているスケッチブックに大野ゆたかのサインが!!
「日の丸一平」の連載終了後、すぐに同誌でSFコミック「少年ロケット隊長」の連載が始まる。(昭和35年~36年まで約6か月間)原作者は豊玉三郎。大野は彼とは会っていない。編集者から原作を渡され、それを漫画に興し続けた。豊田三郎という名前は、東映のTV特撮物のテロップに見受けられるが、同一人物なのか定かではない。
この頃少年誌の連載の多くは2カ月から4カ月程度で終了し、次の作品に切り替わって行くことが多かった時代だった。「日の丸一平」は人気はあったが、そう言った当時の編集方針、紙面に変化を付けて行く、流行を敏感に取り入れるという理由から終了したと推察される。
「少年ロケット隊長」はそんな時節でも比較的長い連載期間を取り、講談社から2巻の単行本にまとめられた。戦記物よりも子供はSF作品により惹かれたのだろう。この本に掲載された部分は講談社単行本第2巻の中盤くらいまでである。2巻が出版された後、本誌少年マガジンの連載はさらに継続し、あと10話ほど単行本未収録の部分が存在している。アップルBOXから発刊される「少年ロケット隊長」第二巻にはその未収録の部分も掲載予定だ。
さて、「荒俣宏の少年マガジン大博覧会」講談社刊(1994年)という本に、1960年少年マガジン掲載コミックで「日の丸一平」「少年ロケット隊長」が紹介されている。その紹介文では、「日の丸一平」は痛快な戦記物で人気を博すが、「少年ロケット隊長」はリアリティに欠け、「日の丸一平」を越えられなかったとコメントされている。
単行本が二巻まで出ている「少年ロケット隊長」の方が読者の人気を取れていたのは歴然としている。「日の丸一平」は人気があったが、単行本は発刊されていないし、連載期間も「少年ロケット隊長」の方が長いのだ。この様なアーカイブ記事でデータを主観で作成することは、後世に残る評価になってしまうので、執筆時の調査は入念に行ってほしい。
「日の丸一平」が週刊連載でのリアリティ溢れる戦記物の始まりであったとするなら、「少年ロケット隊長」はSFコミックの黎明期の作品と言えるだろう。この頃横山光輝の「ロケット部隊」「宇宙警備隊」「宇宙船レッドシャーク」等、宇宙に飛び出していく少年たちの活躍を描いたコミックスが多い。漫画タイトルに「ロケット」をイメージする言葉が多かった。その中で、「少年ロケット隊長」の特色はまず円盤の活躍だろう。
主人公の父親、川上艇長は日本の月ロケット第一号の搭乗員となるものの、ロケットが隕石群と衝突し亡くなる。その意思を継いで主人公川上英雄はロケットパイロットになる訓練を受ける。その訓練機が何故かロケットではなく、円盤なのだ。小型の円盤「ゼロ式円盤」と呼ばれている。そこに敵が現れる。これが「黒い怪円盤」だ。大型の黒い怪円盤には角が三本立っているが、小型の黒い怪円盤はゼロ式円盤とよく似た大きさ、形状(上部に楕円形の突起が二本付いている)をしている。この小型黒い円盤の操縦士からチベットにある円盤を操つる敵基地の存在を知り、英雄はそこに向かっていく。
アップルBOXの第一巻の掲載部分では主人公達も敵も全て円盤に乗った地球人であり、ロケットの存在は無くなったかのようだ。大野はこの頃、UFOのブームがあり、その流行からロケット訓練に円盤を使ったのではないだろうかと話している。
ストーリーの続きでは、宇宙ステーションの建設が始まり、そこに多数のロケットが登場するそうなのだが、そうなるとそれまでの円盤は何だったのだろう? 現代人が考えると、重力をコントロールして飛ぶ円盤の方がロケットよりもハイテクノロジーな気がするのだが。
その疑問はさておき、ロケット隊長は宇宙に出ると宇宙ステーションの建設を始める。それを阻止しようと敵は宇宙軍艦で襲い掛かってくる。押川春浪の「海底軍艦」も宇宙を飛ぶ軍艦だが、宇宙軍艦と言えば「宇宙戦艦ヤマト」があまりにも有名だ。
ヤマトの宇宙での艦隊戦の元になったアイディアはこの「少年ロケット隊長」にあったのではないだろうか?
大野は漫画家として活躍している時期に、手塚治虫から虫プロ入社を勧められ、池袋の虫プロデザイン部に配属になる。同じビルに虫プロの営業部もあり、大野は営業部に西崎義展氏が入社してきた時の記憶が鮮明に残っている。
当時虫プロで毎週行われた企画会議に大野が描いた様な宇宙戦艦がベースになった企画書が提出された事があった。会議ではそれは虫プロ作品の色に合わないと却下された様だが、その企画書を西崎氏は読み、宇宙戦艦が宇宙で戦う戦争物の企画を思い付いたのではないだろうか。その企画を持って、オフィスアカデミーを立ち上げたのではないだろうかと想像される。
「少年ロケット隊長」の第二巻の発刊が待たれる。
「少年ロケット隊長」に描かれた斬新なアイディアは他にもある。厳しい入隊試験と長い訓練生活だ。その後のSF作品では、主人公はすぐにロケットに乗り宇宙に出るとか、ロボットに乗り敵と戦うものばかりだ。本作の様に長い訓練を単行本のほぼ一巻分も描いたりしない。この辺りの描写はSFとはいえ、軍隊の持つ訓練の重要さ、責任感など子供たちが読んで社会性を学ぶのに最適な素材だろう。
もう一つ、ロケットスチュワーデスの女性たちの存在は特筆に値するアイディアだ。特撮TVウルトラマンの第一話で、井出隊員がフジ・アキコ隊員に「所詮女だからな」と彼女には命令遂行の期待値はないと、ぼやくシーンがある。
ジェンダー差別が叫ばれる令和の時代、この様な発言がゴールデンタイムの子供向け番組の電波に乗せて流されていたことは信じがたい。日本では漫画、映像作品の中で女性の扱いは大変差別的だった。そんな時代に、この作品では宇宙飛行の訓練から、実践にも女性隊員の存在の重要性を語っている。傷つき収容された敵の兵士の敵対心も女性たちの人類愛と真心が溶かしてしまうのだ。
この様な時代にあって、ロケットスチュワーデスのエピソードは原作では描かれなかったかもしれない、愛妻家の大野らしい描写になっているのではないだろうか。

▲198ページのイラスト部分拡大。『y.Ohuno』
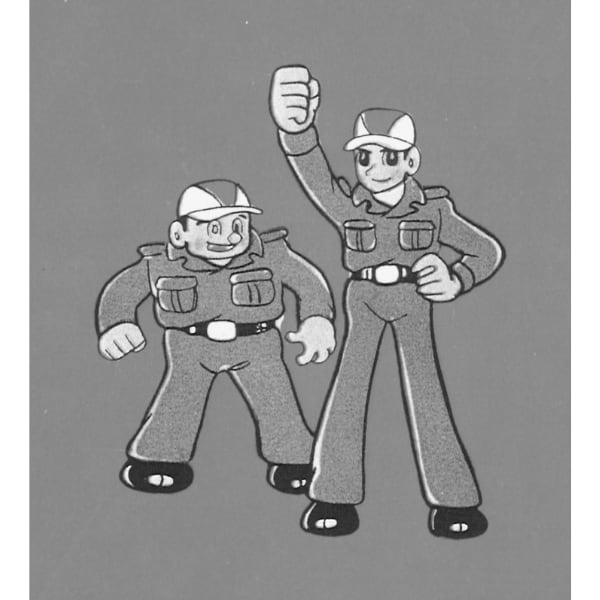
▲少年ロケット隊長の当時の第1巻裏表紙カラー
大野ゆたか創作ノート④ ~虫プロ入社とわんぱく探偵団~

「わんぱく探偵団」グッズ、ぬり絵表紙イラスト
昭和39年(1964年)大野ゆたかは、手塚治虫氏の誘いに応じて、虫プロダクションに入社する。
入社について回想する。
大野は自分が結婚し、子供が出来た事に対し、月刊連載だけの漫画家の収入では家族を満足に養っていけないことを察してくれた手塚氏の温かい配慮があったおかげだと当時を回顧して語る。
大野の入社により、虫プロダクション漫画部は井上チーフの班(4人)、大野チーフの班(4人)の2班のアシスタントチームに編成される。
大野は光文社「少年」連載「鉄腕アトム」、産経新聞連載「ハトよ天まで」などを中心に、手塚氏のアシスタントの仕事に就くことになる。
ある時、手塚氏がヨーロッパに外訪した際、手塚氏に代わって「ハトよ天まで」の代筆原稿を描いたこともあった。
後年大野は、手塚治虫全集に「ハトよ天まで」を収録する際、大野が描いた回は全て手塚氏本人によって、描き直されたと聞いた。
鉄腕アトムテレビ放映50周年記念式典パーティーが池袋メトロポリタンで開かれた、虫プロOBとして大野はそこに出席していた。アニメ部の知人が彼に近づいて話し掛けた。その頃、すでに退社して独立して池袋に仕事場を移していた大野に手塚氏の全集作業での「ハトよ天まで」の描き直しの話を伝えた。
そこで彼には、手塚氏が後世まで残そうと「手塚治虫全集」には並々ならぬ気持ちで作品をブラッシュアップしていることが伝わった。
大野からすればアニメ部にまで、連載当時「ハトよ天まで」の自分の代筆が知れ渡っているのだと言う事を知ったエピソードだ。
言い方を変えると、虫プロの中でも、手塚氏が全権を任せてキャラクターまでも代理で描かせるケースは珍しいことだったのだ。当時、手塚氏が大野の作画力に全幅の信頼を寄せていたことが伺える例のひとつだ。
手塚治虫全集には、手塚氏本人が納得のいかない作品や、連載当時、急いで本来イメージしていた形に描き切れなかった作品を再構成したり、書き直している部分が多い。それは手塚氏の作品に対しての強い思い入れの現れからだ。
虫プロダクションに入社して2年が経過した昭和41年(1966年)に、大野は会社役員会の決定(主に手塚氏の意思が反映される)で、漫画部から池袋東口に新設された虫プロダクション商事に配属替えの辞令を受取る。
(商事の存在を知らない方もいるだろうから簡単に説明すると、TVドラマ「バンパイヤ」のエンディングテロップ等に製作で、「虫プロダクション商事」のクレジットが表記されている。商事は虫プログループの一翼を担った部署だ)
手塚氏はそこにデザイン部、出版部、マーチャンダイジング部(版権部)、を設置し彼にデザイン部部長の待遇を与えた。
大野の仕事に対しての強い責任感とデザインの才能両面を評価の上の抜擢だった。そこで手塚氏は彼に「配属に当たり、漫画部の中で誰でも2名、大野君の好きな者を連れて行って良いです」と条件を付け加えた。
彼はとにかく絵の上手い二人、成田氏(後に講談社から成田マキホのPNで漫画家としてデビュー)、鎌田氏(大野より虫プロ漫画部先輩の実力者)を連れて池袋のデザイン部を立ち上げた。
そこでの主たる仕事は、手塚治虫の漫画、アニメのキャラクターを商品化していくデザインを製作することだった。例えば「鉄腕アトム」のノート、塗り絵、自転車、運動靴のデザインや、玩具会社で制作される立体のデザインの監修等全てデザイン部の仕事になった。
そんな仕事の中で、大野自身のデザインで作られたグッズもある。
虫プロが三和銀行のイメージキャラクターとして制作したのが、(三和銀行から虫プロに発注した)第一弾、「世界の子供達シリーズ」だ。世界の民族衣装を着たかわいい子供たちのキャラクターが貯金箱として立体化した銀行貯金箱グッズだ。数体ほどが数か月ごとに生産され、店頭で新しい預金客などに配られていった。中でもインディアンの子供が、印象的なデザインだ。
後の「ディズニーランド、スモールワールド」の様なイメージの子供キャラクターデザインと表現したらデザインは分かり易いかもしれない。
その後、手塚氏が自ら三和銀行のマスコットキャラクターとして「ワンサくん」という犬のキャラクターをデザインしていろいろな方面に展開していくことになる。
当時の虫プロ商事のビルは、国鉄(JR)池袋駅東口から歩いて4分ほどの大通りに面していた。一階には家電量販店の第一家電店舗があり、2階に虫プロダクション商事の出版部、マーチャンダイジング部(版権部)があり、8階にデザイン部が置かれた。
8階は、和洋室3DKで洋室一室は仕事場として、奥の和室はもっぱら仮眠室に使われていた。その仮眠室には時には仕事明けにアニメ部から集まった関係者たちが麻雀をして、夜明かしをすることもあった。
商事に移転してすぐに、大野は仕事が押せ押せになり多忙を極めた。
睡眠時間が僅かしか取れない日々が始まった。大野は朝まで続く麻雀の騒音に悩まされたが、彼の温厚な性格ゆえに、他部署の社員たちの遊興の時間を制止することはしなかった。
隣室の騒音は眠りを妨げたが、それにも構わず貴重な睡眠時間を確保することに専念した。
彼が商事に転属になった以降も、時々手塚先生の仕事がピンチになると漫画部の助っ人にスタジオのある富士見台に向かう日もあった。
その為、彼は埼玉県所沢に建てた新居に帰れる日が、月を追うごとに少なくなっていった。
大野に虫プロのアニメ作品「わんぱく探偵団」の漫画化の仕事依頼が入ったのは、そんな時だった。
漫画の仕事は天職だと思っていた大野は「わんぱく探偵団」の仕事を喜んで受けるが、それにより、更に自宅に帰れる日が激減してしまう。今にして思い出せば月の内2~3日しか、自宅に戻ることは出来なかった。
この時、大野は30代になり、20代ほど体に無理が利かないことを痛感しはじめていた。
「わんぱく探偵団」の漫画の制作にあたって、渡された企画書には原作江戸川乱歩の名前が入っていた。
しかし、昭和40年(1965年)乱歩氏は池袋の自宅で他界されていた。
それから3年が経過していた。
無論アニメ用の原作原稿などは存在しない。
遺族が漫画化に際して、何かの具体的なストーリーを選定してくれる訳でもなかった。
ただ、虫プロアニメ部の作った設定画が彼の手元に回って来ただけだった。大野は自分なりに小さい頃に読んだ「怪人20面相」「少年探偵団」の数々の小説を思い出し、構想を練った。
そうして、なんとか連載のストーリーを紡ぎ出して行った。

連載漫画「少年探偵団」原作江戸川乱歩、漫画大野ゆたか、扉絵。
そこで唯一参考になったのは虫プロ入社以前4年程前、大野自身が依頼を受け描いた「少年探偵団」(原作、江戸川乱歩)の連載漫画の経験だった。(こちらも明智小五郎、小林少年等が登場する漫画作品)
この作品は、今回の「わんぱく探偵団」の様なアニメ的な絵柄ではなかった。
テレビアニメ「わんぱく探偵団」の制作陣には監督、林重行(りんたろう)、脚本、阿部桂、辻真先など 錚々たるスタッフが参加していた。しかし本作は虫プロが手塚治虫原作なしに始めるテレビアニメーション第一作に相当した。無論その後ベテランに成長していくスタッフも、その時は、まだ経験の浅いアニメ創成期の仕事だった。

「わんぱく探偵団」DVDボックスパッケージ。現在発売中。
「わんぱく探偵団」のフジテレビの放送は、大野の描くコミック版「わんぱく探偵団」の連載(光文社「少年」昭和43年2月から)とほぼ同時に開始された。
連載開始翌月3月に「少年」が突然光文社側の事情で廃刊になってしまう。急遽作品は講談社の「ぼくら」に移転して連載は続けていくことになった。
そんなアクシデントにも大野は揺らがなかった。
作品は前後編で一話完結の形を取り、大野の作画作業は毎日昼間の会議と商事に来たデザイン制作の終わった夜の時間を使って行われた。
大野はアシスタントを使わなかった。面倒くさい背景や、パースを使う車の作画、アクションシーンなども、自分で下描きからペン入れまで作業工程の全てを行った。
その中で、掛け網(丸ペンなどを使う漫画の背景処理)などのバック演出だけは、朝、出社してくるデザイン部のメンバーに埋めてもらった。
フジテレビのアニメ放送の終了に合わせ、ぼくら10月号で「わんぱく探偵団」連載は終了になるが、(今回のアップルBOX復刻に当たり、第2巻掲載になっている)付録「消えた新幹線」前後編の前の話は収録されている。最終回「消えた新幹線」の回は、当時来日していたインドネシアのスカルノ大統領とデビ夫人がモデルになった(スルガノ大統領)大統領夫妻が登場する。日本人の大統領夫人と言うデビ夫人の当時の話題性を彷彿とさせるエピソードだ。彼らが搭乗した新幹線が走行中、20面相のたくらみでトンネルに入ったまま消えてしまうのだ。
それまで、わんぱく探偵団に毎回負け続けていた怪人20面相は、探偵団をあっと言わせる一大トリックで探偵団に一泡吹かせようと考えたのだ。
無論20面相としては表向き、大統領夫人の妻の首に掛けられた大粒の宝石が目当てと言う事にしているが、それも探偵団の鼻を明かすための盗みの口実に過ぎない。
「わんぱく探偵団」連載の最終話に当たるこの事件で、20面相をとことん追い詰めるが、そこで20面相の生死が定かでないまま、この物語は終劇になる。
大野ゆたかはデビュー以来貸本屋時代の書き下ろし作品「アルセーヌ・ルパン」2巻、「少年探偵団」、「わんぱく探偵団」と、漫画家になって、何度も怪盗紳士を作品化していく中で推理サスペンスの世界を確実に築き上げていった漫画家だ。
他にも「秘密警察27」(少年サンデー短期連載作品)等がある。この作品は掲載後数年して同じ作品タイトルで、同誌サンデーで岸本修氏が執筆している。特に大野のコミック作品との関連性は無い。
当時、20面相は変装の名人、盗みは働くが、人殺しはしないと言う人物像で子供たちの人気者になった。
それを引き継いでいったのが、その後双葉社で連載の始まる「ルパン三世」著モンキー・パンチだろう。人殺しはしない、変装の名人、怪盗ルパン三世の世界ではヒーロールパン三世に仲間が加わり、更に子供たちの人気を不動にしていくサスペンスアクションの世界が構築されていく。
大野が「わんぱく探偵団」の連載を、寝る間を惜しんで描き続けていた頃、虫プロの役員会では、「大野は虫プロの社員と、漫画家の二足の草鞋を履いている。給料の2重取りだ。それはけしからん」と言う発言が出て、議論をかもし出した。
それに対し手塚氏は怒りを込めて反論した。
「僕は虫プロに漫画家の大野ゆたか氏を雇ったのだから、大野が漫画を描くのは当たり前だ。それにデザイン部の仕事も立派にこなしてくれている」と大野をおおいに擁護してくれたことを、後日彼は役員の一人から聞かされた。
大野はこの手塚氏の言葉に、今でも深く感謝している。
ここからは、大野が接していた恩師手塚治虫が創作活動に挑む姿勢について、彼が数々の感銘を受けた回想になる。
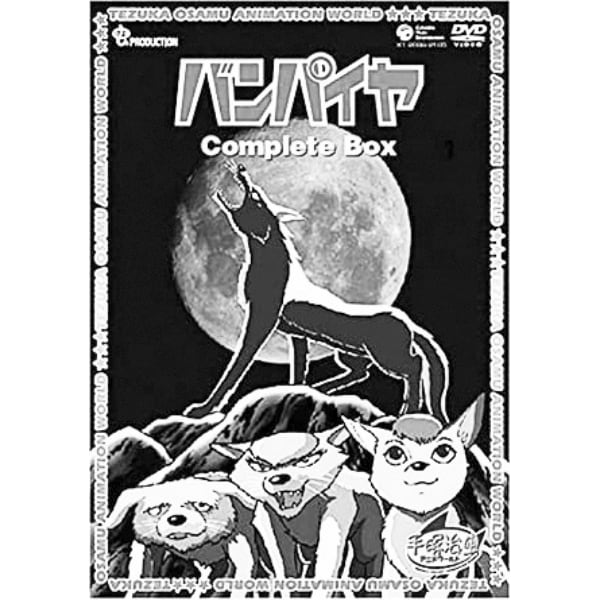
「バンパイア」DVDボックス。現在発売中。
フジテレビの「わんぱく探偵団」の後番組は「バンパイア」だ。手塚治虫、少年サンデー連載作品の実写映像化だ。
バンパイアは実写ドラマにアニメ合成の特撮シーンで動物の動きや人から獣への変身シーンを合成するなどの画期的な試みを多用した作品だった。
それが僅か3か月で終了してしまうのは、手塚治虫ファンとしては大変残念なことだった。
物語はバンパイヤは主人公の狼に変身できる少年トッペイが、一族が長きに渡り隠れ住んでいた呪われた村を焼き払い、たった一人で上京し、手塚プロダクションに漫画のアシスタントとして就職するところから始まる。
主人公のトッペイを演じたのが、若き日の水谷豊だ。劇団ひまわりに席を置いていた水谷氏は1968年のフジテレビオーディションで主役に抜擢される。彼はテレビドラマ第一話で手塚治虫本人と共演する。
そのロケの現場になったのは池袋、虫プロダクション商事の2階の仕事場だった。大野はその撮影を興味深そうに見ていた。
アニメの創成期に数々の傑作アニメが作られたが、その中には手塚治虫作品だけでなく、競い合う様に多くのクリエイター達の作品がテレビ局の企画会議のテーブルに挙がった。
手塚治虫が虫プロ社内の新作のアニメーション企画会議を重ねていく中で、彼の得意分野SFアニメのアイディアが多数企画書にまとめ上げられていた。
例えば「宇宙戦艦ヤマト」もアニメ部から提出された企画書の一つだ。大野は富士見台の仕事場でそれを見ている。当時それは、虫プロ的に向かない企画と言う事で、社内でお蔵入りになった。
時を経て、1974年頃商事を離れた大野に旧友の松本零士氏から、電話で問い合わせがあった。「西崎義展と言う男は、どういう人物なのか?」という内容だった。
宇宙戦艦ヤマトの製作が始まる段階で、製作の依頼を受けた松本氏が同郷の大野に西崎氏の人柄を尋ねた。その電話に大野は「彼は自分の企画を強引に進める人物だ。だから、めったなことで折れてはいけない。自分の考えはまげない事です」と答えた。大野は言う、
「ヤマト」というタイトルは虫プロの社内プレゼンの企画書に既に存在していた。その作品の細部のストーリーは、松本氏の創作であると。
またある時、その企画書がテレビ局に提出される直前、別局で「宇宙少年ソラン」の放送が決定し、その内容を知って、手塚氏は頭を抱えたと言う。
彼が企画書に描いたアイディアがほとんど同じ形で使われていたのだ。果たしてそれは偶然だったのだろうか?
「この企画の前に、少年と宇宙からきたリスのシリーズを考えたのです。ところが、その企画そっくりのものが他の製作会社で作られていることがわかり(これが、「宇宙少年ソラン」になりました)虫プロの中に産業スパイがいるのではないかという役員会の疑いがおこり…」云々、手塚治虫全集「W3」あとがきに書かれている。
手塚氏は手塚治虫全集の「アバンチュール21」のあとがきの中で、 「ぼくは、主人公のうさぎに非常に愛着を感じているので、何度でも登場させてやりたいです」、作品に登場する可愛いウサギのキャラクターについて、強い愛着を語っていることを強調している。
W3ではリスに替えて、うさぎを登場させている。
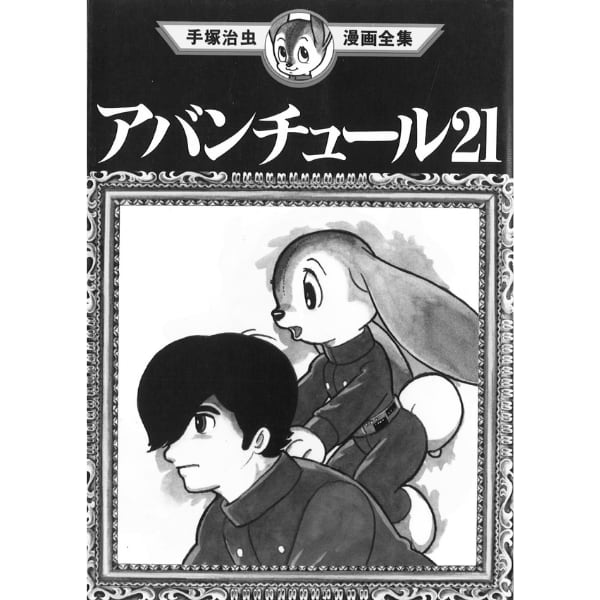
「アバンチュール21」漫画単行本表紙、手塚治虫全集より。
SF的設定の可愛い小動物のキャラクターに、初期の赤本時代から強いこだわり持っていたことが伺える。
他局の放映予告を目にした手塚氏はフジテレビ局の企画会議の締め切りに間に合わせるように、急遽企画書を書き直して提出することになった。
その企画書が「W3」だった。(フジテレビ1965年6月6日スタート、全52話)
この盗作疑惑が手塚氏の脳裏に湧きあがった理由は、虫プロの企画会議に某氏(「宇宙少年ソラン」コミック漫画家)が出席していたためだろう。
「W3」は、こうしたアクシデントの他にも、作品連載誌を途中で変更するなど、不安定な境遇で世に出た作品だった

「W3」漫画単行本表紙、手塚治虫全集より。
しかしその完成度の高さは漫画、アニメーション共に素晴らしいものだった。その時手塚治虫と言う巨人が逆境をバネにして素晴らしい創作が出来る漫画の神様の底力を見せつけられたような気がした。
大野が見ていた天才手塚治虫は、常に漫画界のトップを走り続けていかないと気が済まない負けず嫌いな性格の持ち主だったようだ。
氏のエッセイなどでは有名な話だが、少年マガジンで「ゲゲゲの鬼太郎」がアニメ化され大ヒット(驚異的視聴率48%を記録)すると、手塚氏はその負けず嫌いの性格が頭をもたげたようだ。
彼は少年サンデーで不朽の名作伝奇妖怪コミック「どろろ」を描く。
同じ妖怪をテーマに扱った作品でも、全く違う世界観で手塚氏は自分の妖怪世界を創り上げていった。
どろろの背景処理を見ると、鬼太郎の背景の様な描写処理を取り入れようとした影響が随所に見られると、大野は指摘する。
また、永井豪が「ハレンチ学園」で、小学生の性の解放を謳い上げ、マスコミの話題を独占し、少年ジャンプの部数を伸ばすと、手塚氏はそれは邪道だと言い切った。
お色気で子供たちの心を掴むことでは、純真な青少年に対する性教育が歪んでしまう事を危惧したのだ。
漫画が悪書にされかねないと嘆いたと聞く。
手塚氏は性を正面から教える漫画が世にあるべきだと「アポロの歌」「やけっぱちのマリア」「不思議なメルモ」などを描き始めたと言う。
石森章太郎が「ジュン」などで、漫画の大胆なコマ使い、見開きの表現、立てや横のコマ割り、で読者魅了すると、「見開きの乱用など邪道だ」と言いながらもコマの演出を使った表現をさりげなく自分の漫画に取り入れて行った。
手塚氏の心の中には、自分こそが日本の戦後の漫画の創成期からトップを走り続け、漫画界を伸ばしてきたのだと言う自負があった。
手塚氏は自分の中にそれまで持っていなかった才能に対しては、後に続いてくる漫画家たちの活躍に反発しながらも、話題作品を研究し、自ら進んで取り入れて、吸収し、自分の物にしていこうと言う挑戦心が常に持ち続けていた。
大野は言う。「皆さんは僕のことを天才だというけれど、僕は努力家なんだよ」と手塚氏から言われたことを思い出します。
それを生涯持ち続けて行った人だからこそ、手塚治虫は天才の地位を不動のものにしたのだろう。
それだからこそ、数々の名作が手塚氏の手で生み出され、漫画界の第一線で作品を描き続けられたのだろうと、大野は虫プロダクション時代、手塚治虫漫画部のチーフだった過去を回想する。
虫プロダクションが倒産する半年ほど前、デザイン部に来る仕事量は激減していた。大野はそこでデザイン部を退社し、池袋東口側にマンションを借りて、デザイン事務所を開設した。

「W3」講談社、少年マガジン版、W3(単行本未掲載部分、総集編)1997年8月22日発行。表紙と裏表紙。





